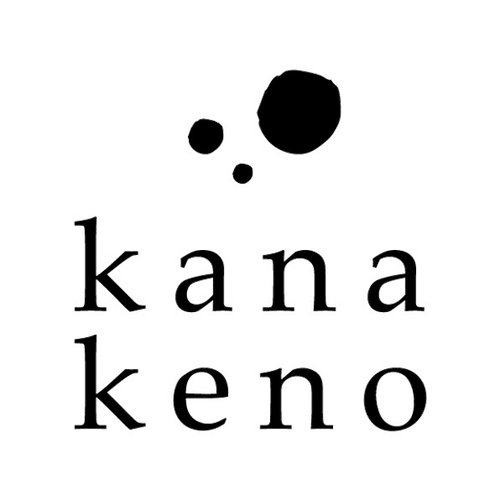丁寧を育む、てつびん生活
たとえば、15分だけ早く起きて
鉄瓶でお湯を沸かす。
まろやかなお湯で淹れたコーヒーで迎える、
いつもよりちょっと贅沢な朝。
kanakenoで、そんな丁寧な暮らし、
はじめてみませんか。

暮らしに馴染むデザイン
kanakenoの鉄瓶は、伝統的な鉄瓶の風合いを残しつつも、現代生活にとけこみやすいデザインとなっています。
日々の生活でストレスなく使えるように、注ぎやすさにこだわった注ぎ口と、手作りならではの誰でも扱いやすい軽さを実現しました。また、IHでも使用可能で、あかいりんごについては取手が折り畳める仕様になっています。

実は使いやすく、使うほどに価値が出る
鉄瓶は扱いづらそう、というイメージがあるかもしれませんが、実はとても簡単です。沸かしたら使い切って乾かしておくだけ。お湯しか沸かさないので、まったく洗いません。
そして使えば使うほど、鉄瓶の内側に「湯垢(ゆあか)」が付いていきます。これは決して汚いものではなく、むしろ、湯垢が付けば付くほど、白湯の味わいがまろやかになっていきます。そうして鉄瓶を使い続けて内側に湯垢をつけていくことを私たちは「育てる」と言っています。

安心サポートサービス
kanakenoの鉄瓶をご購入いただいた方には、2つのサポートサービスをご用意しています。
1つは、2回までお直し無料の「生涯保証サポート」。鉄瓶は、たとえ深くさびつくなどがあっても、状態を回復させられるほどとても丈夫なものです。さびることを恐れずに、日々の生活の中でどんどん使っていただければと思います。
2つ目は、鉄瓶コンシェルジュにLINEで気軽に相談できる「日常サポート」。日々お使いいただく中での疑問にお気軽にご相談いただけるようにと、LINEでのサポートを行っています。もちろん、電話やメール等でもお気軽にご相談いただけます。

健康的な生活へ
鉄瓶で沸かしたお湯はやわらかく、まろやかな味わいになります。そして鉄分補給にもなるので貧血の方や妊婦さんにもおすすめです。
白湯だけではありません。
想像してみてください。朝15分早く起きて鉄瓶を沸かすという生活を。
鉄瓶を生活に取り入れることが、ライフスタイルを整えるきっかけにもしていただけたら幸いです。

信頼できる「伝統的な価値」
kanakenoの職人たちは、技術顧問の田山和康(南部鉄器伝統工芸士会会長/日本伝統工芸士会常任幹事/現代の名工)から指導を受けながら鉄瓶を制作し、そして、さらに高みを目指せるように日々修業をしています。
田山和康は、2019年の天皇陛下のご即位に際して献上品の鉄瓶制作を岩手県から依頼されているほどの業界最高レベルの技術の持ち主です。
職人たちはその師匠の下、技術を吸収し続けています。

若手職人の育成
名工の技術を後世にも途絶えることなく伝えていこうと、私たちは「あかいりんごプロジェクト」という、若手職人が早い段階で鉄瓶制作の全工程に携われる取り組みをしています。
こうした若手職人の育成や、そのプロダクトの品質を評価いただき、第3回三井ゴールデン匠賞を受賞することができました。

楽しい生活をつくること
私たちは、鉄瓶を使うことが「豊かな生活」や「楽しい」に繋がっていってほしいと思っています。
kanakenoの鉄瓶ユーザー向けにLINEで日々の情報提供を行ったり、「てつびんの学校」という講座を開くなど、ユーザーの方々とともに、鉄瓶生活もアップデートし続けていきます。
ぜひ、みなさんも一緒にこの「てつびん生活」を楽しんでみませんか?
製品一覧
よくあるご質問FAQ
Q. 鉄瓶はIHでも使えますか?
A. はい、IHでも使用可能です。
kanakenoの鉄瓶は、ガスコンロ、IH、反射式ストーブ、キャンプ用ガスバーナー、炭火等、ほとんどの熱源で使用可能です。
※IHで鉄瓶をお使いになる方は、ご使用のIHの対応底径サイズをご確認ください。底径のサイズが対応外ですと、反応しない場合がございます。
kanakenoの鉄瓶の底径は8cm~8.5cmとなります。詳しくは製品仕様一覧をご覧ください。
Q. 鉄瓶白湯で鉄分補給ができるって本当ですか?
A. 鉄瓶で沸かした湯には鉄分が溶出し、その多くが体に吸収されやすい二価鉄であると学術的に証明されています。
鉄瓶白湯を飲むことで自然な形で鉄分補給ができ、毎日の生活に無理なく取り入れることができます。毎日のお食事と共に補助的に使っていただくことをオススメいたします。
ただし、鉄瓶の内側にホーロー加工が施されている鉄瓶は 鉄分補給ができませんので、ご購入の際にはご注意ください。
※kanakenoの鉄瓶は全て鉄分補給ができるよう製造されています。
Q. 沸かすお水は何を使えば良いですか?
A. ご自宅の水道水をお使いいただいて大丈夫です。
水道水を鉄瓶で沸かすとカルキ臭が和らぎ、湯がまろやかで美味しい白湯を作ることができます。(※お住まいの地域によって多少異なります。)
詳細はこちらの「基本的な使い方」をご覧ください。